未就労年少者の逸失利益の計算方法は?
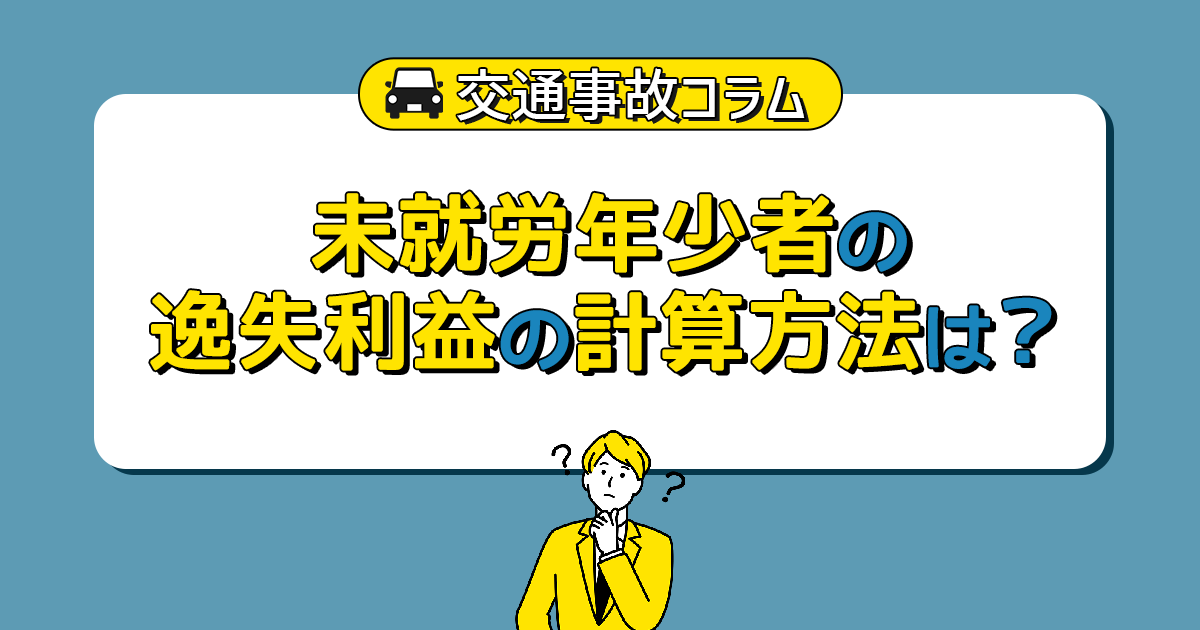
交通事故で後遺症が残ったり、亡くなったりした場合には、加害者に対して逸失利益の賠償を請求できます。
逸失利益は、交通事故当時の収入をベースとして、将来得られるはずであった利益を請求するものです。しかし、未就労年少者の場合、ベースとなる収入がありません。
この記事では、収入のない未就労年少者でも逸失利益を請求できるのか、請求できるとしてどのように計算するのかについて解説します。逸失利益は、交通事故の賠償金の中でも大きな割合を占める重要な要素です。逸失利益の算定に不安のある方は、ぜひ最後までご覧ください。
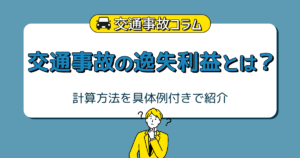
未就労年少者でも逸失利益を請求できる
未就労年少者でも、成長して将来的には収入を得る見込みがあるため、逸失利益を請求できます。
逸失利益は、交通事故当時の収入を基礎収入として計算するのが原則です。ただし、事故当時に就労していなかった者については、就労を開始した場合に見込まれる収入額を基礎収入として逸失利益を計算します。
未就労年少者の場合、基礎収入は、賃金センサスの学歴計・男女別の全年齢平均賃金を採用するのが原則です。ただし、被害者の状況によっては、別の基準を採用することもあります。
たとえば、被害者が大学生の場合や大学に進学する蓋然性が認められる場合には、学歴計ではなく学歴別の大学卒の全年齢平均賃金を採用します。また、被害者が専門教育を受けており、卒業後に特定の職業に就く蓋然性が認められるときには、職業別の全年齢平均賃金が採用されるケースが多いでしょう。
未就労年少者の逸失利益の計算方法
逸失利益には、被害者が死亡した場合の死亡逸失利益と、被害者が後遺障害を負ったときの後遺障害逸失利益の2つがあります。
ここでは、死亡逸失利益と後遺障害逸失利益に分けて、未就労年少者の逸失利益の計算方法を解説します。
未就労年少者の死亡逸失利益
死亡逸失利益は、基礎収入から被害者の生活費を控除したものに、就労可能年数に応じたライプニッツ係数を乗じて算定します。
未就労年少者の基礎収入については、前述のとおりです。基礎収入から生活費を控除するのは、被害者が亡くなったことで必要な生活費の支払いがなくなるためです(生活費は被害者が生存していた場合でも手元に残らないものなので、差し引いたうえで計算します)。
生活費として控除される割合は、未就労年少者が男性の場合は50%、女性の場合は30%が基準となります。ただし、女性の場合でも、基礎収入を男女計の平均賃金とする場合には、45%程度が生活費控除の基準です。
就労可能年数に応じたライプニッツ係数は、学歴計の平均賃金を採用する場合、死亡時から67歳までに対応するライプニッツ係数から、死亡時から就労開始年齢までの年数に対応するライプニッツ係数を差し引いたものとなります。
たとえば、被害者が10歳で死亡した場合、10歳から67歳までの57年に対応するライプニッツ係数から、就労開始年齢である18歳までの8年に対応するライプニッツ係数を差し引いたものが、就労開始年齢に応じたライプニッツ係数となります。
なお、基礎収入について大学卒の平均賃金を採用する場合には、就労開始年齢を22歳として計算する必要があるため注意が必要です。
未就労年少者の後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は、基礎収入に労働能力の喪失割合を乗じたものに、労働能力の喪失期間に応じたライプニッツ係数を乗じて計算します。
労働能力喪失率は、後遺障害認定の等級を基準に、障害の部位や程度、被害者の年齢や性別などを総合的に考慮して判断されます。
たとえば、「男子の外貌に著しい醜状を残すもの」については、後遺障害12級に認定されるものですが、醜状は一般的な職業における労働能力の喪失に直結するものではないため、労働能力喪失率は、14%よりも低く認定されるケースが多くなるでしょう。
労働能力の喪失期間は、原則として就労開始年齢から67歳までの期間となります。ただし、将来的に症状の緩和が見込まれるむち打ち症の場合には、後遺障害12級の場合で5年から10年、14級の場合で2年から5年が喪失期間の目安となります。
逸失利益の計算については弁護士への相談がおすすめ
逸失利益を計算するには、被害者の年齢だけでなく、さまざまな事情を考慮しなければなりません。特に、基礎収入に何を採用するのか、労働能力喪失率をどの程度とするのかなどについては、専門的知識がなければ判断が難しいでしょう。
逸失利益は、交通事故の賠償金の中でも大きな割合を占めるものです。正確な判断をするためにも、逸失利益の計算に不安がある場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

