後遺障害等級第7級の主な症状と認定基準・慰謝料相場について
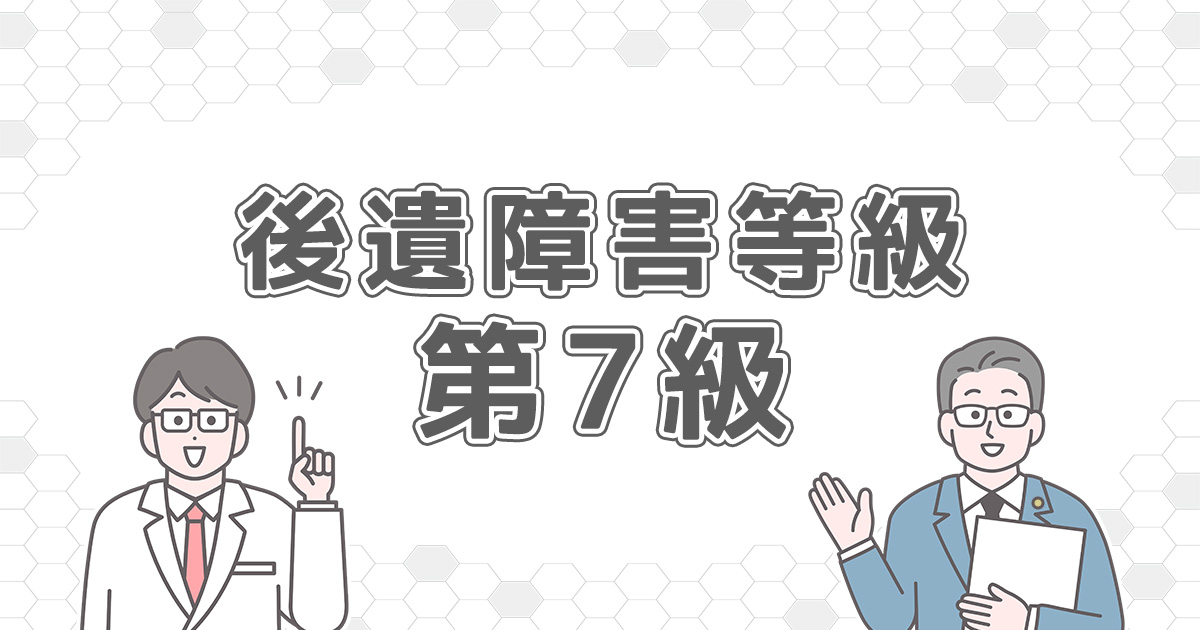
交通事故で後遺症が発生した場合、後遺障害等級認定を受けます。後遺障害等級認定は後に保険会社に対して行う損害賠償請求に大きな影響を及ぼすので、適切な等級認定を受けることが欠かせません。
本記事では、後遺障害等級第7級について、認定の対象となる主な症状と認定基準・慰謝料などについて解説します。
後遺障害等級第7級
後遺障害等級第7級については「自動車損害賠償保障法施行令 別表第2」で次のように定められています。
自動車損害賠償保障法施行令 別表第2
- 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
- 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
- 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
- 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
- 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
- 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
- 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 両足の足指の全部の用を廃したもの
- 外貌に著しい醜状を残すもの
- 両側の睾丸を失つたもの
一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
怪我によって「一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの」に該当する場合には後遺障害等級第7級の認定がされます。
他にも目の怪我によって次のような等級に認定される可能性があります。
- 両眼が失明した:第1級
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下:第2級
- 両眼の視力が0.02以下:第2級
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下:第3級
- 両眼の視力が0.06以下:第4級
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下:第5級
- 両眼の視力が0.1以下:第6級
- 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下:第8級
- 両眼の視力が0.6以下:第9級
- 一眼の視力が0.06以下:第9級
- 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの:第9級
- 一眼の視力が0.1以下:第10級
- 正面を見た場合に複視の症状を残すもの:第10級
- 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの:第11級
- 両眼のまぶたに著しい運動障害を残す:第11級
- 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの:第11級
- 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残す:第12級
- 一眼のまぶたに著しい運動障害を残す:第12級
- 一眼の視力が0.6以下:第13級
- 正面以外を見た場合に複視の症状を残す:第13級
- 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残す:第13級
- 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残す:第13級
- 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残す:第14級
両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
怪我によって「両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」に該当する場合には後遺障害等級第7級の認定がされます。
「両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」と認定されるのは次のいずれかです。
- 耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上、かつ、最高明瞭度が50%以上のもの
聴力の後遺症がこの状態に達していなくても、次の認定がされる場合があります。
- 両耳の聴力を全く失った:第4級
- 耳に接しなければ大声を解することができない程度になった:第6級
- 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった:第6級
- 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった:第9級
- 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になった:第9級
- 一耳の聴力を全く失ったもの:第9級
- 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になった:第10級
- 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になった:第10級
- 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になった:第11級
- 一耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった:第11級
- 一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になった:第14級
一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
怪我によって「一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」に該当する場合には後遺障害等級第7級の認定がされます。
「一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」と認定されるのは、片方の耳の平均純音聴力レベルが90dB以上で、もう片方の耳の平均純音聴力レベルが60dB以上の状態をいいます。
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
怪我によって「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」に該当する場合には後遺障害等級第7級の認定がされます。
高次脳機能障害・外傷性脳損傷・脊髄損傷などで認定されます。
高次脳機能障害の場合には次の4つの能力のうち、1つの能力が半分程度失われているか、2つ以上の能力が相当程度が失われている場合に第7級の認定がされます。
- 意思疎通能力
- 問題解決能力
- 作業負荷に対する持続力・持久力
- 社会行動能力
外傷性脳損傷によって身体性機能障害として次の症状があると第7級の認定がされます。
- 軽度の片麻痺が認められるもの
- 中等度の単麻痺が認められるもの
脊髄損傷の場合、次の症状があると第7級の認定がされます。
- 一下肢の中等度の単麻痺
ほかにも次のようなケースで第7級に認定されることがあります。
- 外傷性てんかんで転倒する発作等が数ヶ月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1ヵ月に1回以上ある
- 失調、めまい及び平衡機能障害中等度の失調又は平衡機能障害のために、労働能力が一般平均人の1/2以下程度に明らかに低下しているもの
- カウザルギーについて軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛がある
- 反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)については、軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛がある
神経系統の機能又は精神の障害の程度によって次のような等級に認定されることがあります。
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの:第1級
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの:第2級
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの:第3級
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの:第5級
- 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの:第9級
- 局部に頑固な神経症状を残すもの:第12級
- 局部に神経症状を残すもの:第14級
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
怪我によって「胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」に該当する場合には後遺障害等級第7級の認定がされます。
胸腹部臓器とは、呼吸器・循環器・腹部臓器・泌尿器・生殖器などです。
第7級に認定されるものとして次のものが挙げられます。
- 動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下で、脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr~43Torr以外)にない
- スパイロメトリーの結果が%1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であり、呼吸困難の程度が中等度(呼吸困難のため、平地でさえ健常者と同様には歩けないが、自分のペースでなら1km程度の歩行が可能である)にある
- スパイロメトリーの結果が%1秒量が35を超え55以下又は%肺活量が40を超え60以下である場合で、呼吸困難の程度が高度(呼吸困難のため、連続しておおむね100m以上歩けない)または中等度にある
- 除細動器を植え込んだ
- 胃の切除によって、消化吸収障害、ダンピング症候群及び胃切除術後逆流性食道炎のすべてが認められる
- 人工肛門を造設した場合で「小腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの」に該当しない
- 小腸皮膚瘻を残す場合で、「小腸内容が漏出することにより小腸皮膚瘻周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの」に該当しない
- 小腸皮膚瘻を残す場合で、瘻孔から漏出する小腸内容がおおむね100ml/日以上でありパウチ等による維持管理が困難である場合
- 完全便失禁を残す
- 一側のじん臓を失っ場合でGFRが30ml/分を超え50ml/分以下GFR値が30超~50
- 非尿禁制型尿路変向術を行った場合で、「尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パッド等の装着ができないもの」に該当しない
- 禁制型尿リザボアの術式を行った
- 切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁によって終日パッド等を装着し、かつ、パッドをしばしば交換しなければならない
胸腹部臓器の機能の障害については他に下記のような認定がされる可能性があります。
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの:第1級
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの:第2級
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの:第3級
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの:第5級
- 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの:第9級
- 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの:第11級
- 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの:第13級
一手のおや指を含み三の手指を失ったもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの
怪我によって「一手のおや指を含み三の手指を失ったもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの」に該当する場合には後遺障害等級第7級の認定がされます。
「手指を失ったもの」とは、親指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったことをいい、具体的には次の通りです。
- 手指を中手骨又は基節骨で切断した
- 近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断した
指の後遺症には他にも次のようなものがあります。
- 両手の手指の全部を失った:第3級
- 両手の手指の全部の用を廃した:第4級
- 一手の五の手指又は親指を含み四の手指を失った:第6級
- 一手の親指を含み二の手指を失った又は親指以外の三の手指を失った:第8級
- 一手の親指を含み三の手指の用を廃したは親指以外の四の手指の用を廃した:第8級
- 一手の親指又は親指以外の二の手指を失った:第9級
- 一手の親指を含み二の手指の用を廃した又は親指以外の三の手指の用を廃した:第9級
- 一手の親指又は親指以外の二の手指の用を廃した:第10級
- 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの:第11級
- 一手の小指を失ったもの:12級
- 一手の親指以外の手指の指骨の一部を失った:14級
- 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなった:14級
一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
怪我によって「一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの」に該当する場合には後遺障害等級第7級の認定がされます。
「手指の用を廃した」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)に著しい運動障害を残すものであり、具体的には次の状態をいいます。
- 手指の末節骨の長さの1/2以上を失った
- 中手指節関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限される
- 親指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されている
- 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失した
一足をリスフラン関節以上で失ったもの
怪我によって「一足をリスフラン関節以上で失ったもの」に該当する場合には後遺障害等級第7級の認定がされます。
「リスフラン関節以上で失った」とは次のいずれかをいいます。
- 踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる足根骨において切断した
- リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断した
両足をリスフラン関節以上で失うと、第4級の認定がされます。
一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
怪我によって「一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第7級の認定がされます。
「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、常に硬性補装具を必要とするもので次のいずれかのことをいいます。
- 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの
- 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
その他上肢の怪我による後遺症では次の障害等級が認定されます。
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの:第1級
- 両上肢を手関節以上で失った:第2級
- 一上肢をひじ関節以上で失った:第4級
- 一上肢を手関節以上で失ったもの:第5級
- 一上肢の用を全廃した:第5級
- 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃した:第6級
- 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃した:第8級
- 一上肢に偽関節を残す:第8級
- 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残す:第10級
- 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残す:第12級
一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
怪我によって「一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第7級の認定がされます。
「下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」に次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。
- 大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
- 脛骨及び腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
- 脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
下肢の怪我に関する後遺障害等級にはほかにも次のものがあります。
- 両下肢をひざ関節以上で失った:第1級
- 両下肢を足関節以上で失った:第2級
- 一下肢をひざ関節以上で失ったもの:第4級
- 一下肢を足関節以上で失ったもの:第5級
- 一下肢の用を全廃した:第5級
- 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃した:第6級
- 一下肢を5cm以上短縮した:第8級
- 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃した:第8級
- 一下肢に偽関節を残した:第8級
- 一下肢を3cm以上短縮した:第10級
- 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残す:第10級
- 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残す:第12級
- 一下肢を1cm以上短縮した:第13級
両足の足指の全部の用を廃したもの
怪我によって「両足の足指の全部の用を廃したもの」に該当する場合には後遺障害等級第7級の認定がされます。
「両足の足指の全部の用を廃したもの」とは第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいい、具体的には次の状態をいいます。
- 第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失った
- 第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断した又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断した
- 中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指の場合は指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限される
外貌に著しい醜状を残すもの
怪我によって「外貌に著しい醜状を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第7級の認定がされます。
「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部など、上肢や下肢以外で日常的に露出する部分を指します。「外貌に著しい醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当し、人目につく程度以上のものを指します。
- 頭部の場合は、てのひら大の瘢痕または頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
- 顔面部の場合は、鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没
- 頸部の場合は、てのひら大以上の瘢痕
外貌に関する後遺症については他にも次の等級に認定される可能性があります。
- 外貌に相当程度の醜状を残すもの:第9級
- 外貌に醜状を残すもの:第12級
- 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの:第14級
- 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの:第14級
両側の睾丸を失ったもの
怪我によって「両側の睾丸を失ったもの」に該当する場合には後遺障害等級第7級の認定がされます。
「睾丸を失った」とは、睾丸を事故や手術で切断した場合をいいます。
次の場合に準用されることも知っておきましょう。
- 常態として精液中に精子が存在しないもの
- 両側の卵巣を失ったもの
- 常態として卵子が形成されないもの
複数の後遺症によって第7級と認定される場合もある:併合
上記の症状がなくても、複数の軽い後遺症が重なって第7級と認定される「併合」という仕組みがあります。
後遺症が複数ある場合、それぞれの後遺症が第7級よりも軽い場合でも、それらを併せて第7級に認定されることがあります。これが併合のシステムです。
例えば、第8級の症状と第9級~13級の症状がある場合、第8級が1つ上がり、第7級となります。
具体的に該当しない場合でも第7級と認定される場合もある:相当
具体的に第7級の等級に規定されている場合ではなくても、症状から第7級に認定する「相当」という仕組みがあります。
後遺障害等級認定は、後遺障害等級表に規定されていなくても、第7級に相当するような症状がある場合には、第7級として取り扱う場合があります。これが「相当」です。
後遺障害等級第7級の後遺障害慰謝料
後遺障害等級第7級の後遺障害慰謝料は次の通りです。
| 基準 | 後遺障害慰謝料の額 |
| 自賠責基準 | 419万円(※2020年3月31日までは409万円) |
| 任意保険基準 | 450万円~600万円程度(※保険会社による) |
| 弁護士基準(裁判基準) | 1,000万円 |
保険会社が提示する任意保険基準は、裁判所で認定される弁護士基準の半分以下になることがあります。そのため、示談交渉の際には、必ず弁護士基準で再計算し、適切に交渉することが重要です。
後遺障害等級第7級の労働能力喪失率
後遺症が残ったときには後遺障害逸失利益の請求ができます。
後遺障害逸失利益の計算は次の計算式によって行われます。
| 基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 |
後遺障害等級第7級に認定された場合、労働能力喪失率は、56/100として計算されます。
まとめ
本記事では、後遺障害等級第7級の主な症状と認定基準・慰謝料相場などについて解説しました。
後遺障害等級第7級の労働喪失率は56/100であり、労働能力の半分以上を欠く重篤な後遺症が残っている状態です。そのため、後遺障害等級認定を確実に取得してその後の生活に備える必要があります。
慰謝料についても弁護士基準で再計算することが重要であり、さらに過失割合などの他の要素についてもきちんとした交渉が必要です。なるべく後遺障害等級認定のサポート段階から弁護士に相談して、適切な示談金を得ましょう。

