後遺障害等級第9級の主な症状と認定基準・慰謝料相場について
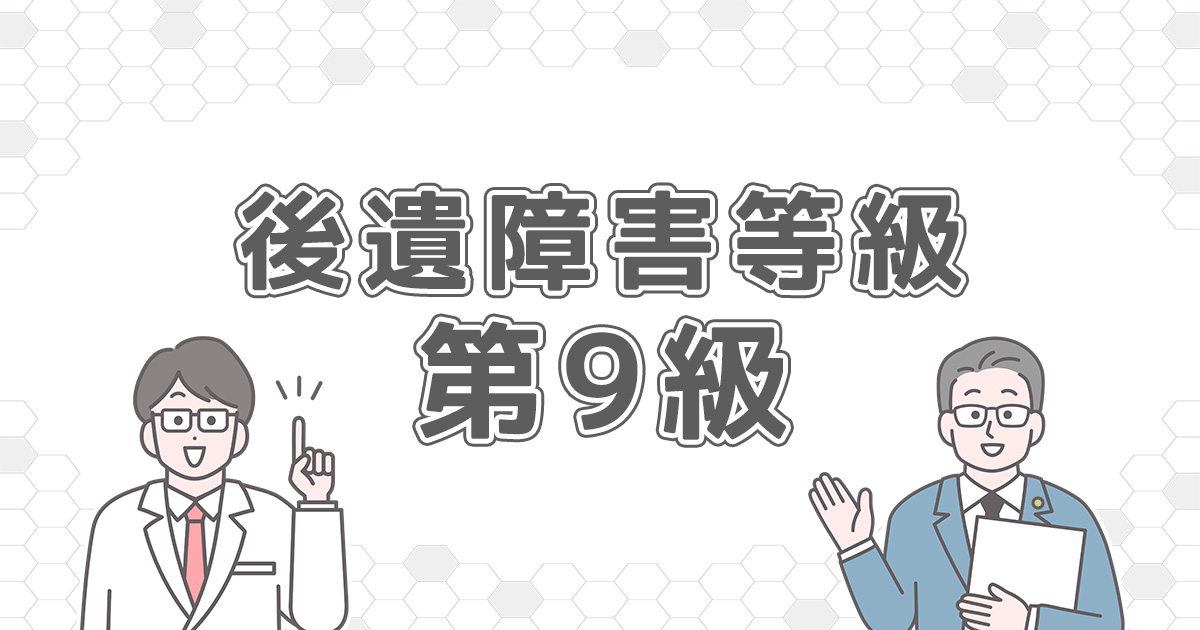
大きな事故に遭うと後遺症が残ってしまうことがあります。治療を尽くして症状固定となった後には後遺障害等級認定を行なうことになります。何級に認定されるかによって、慰謝料や逸失利益の額に大きな影響があり、後遺症が残る場合の損害賠償の大きな争点となります。
本記事では、後遺障害等級第9級の主な症状と認定基準・慰謝料について解説します。
後遺障害等級第9級
後遺障害等級第9級については「自動車損害賠償保障法施行令 別表第2」で次のように定められています。
自動車損害賠償保障法施行令 別表第2
- 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
- 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
- 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
- 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
- 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
- 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
- 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
- 一耳の聴力を全く失つたもの
- 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
- 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
- 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
- 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
- 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
- 一足の足指の全部の用を廃したもの
- 外貌に相当程度の醜状を残すもの
- 生殖器に著しい障害を残すもの
両眼の視力が0.6以下になったもの
怪我によって「両眼の視力が0.6以下になったもの」に該当する場合には後遺障害等級第9級の認定がされます。
目の後遺症については他にも次のものが挙げられます。
- 両眼が失明した:第1級
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下:第2級
- 両眼の視力が0.02以下:第2級
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下:第3級
- 両眼の視力が0.06以下:第4級
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下:第5級
- 両眼の視力が0.1以下:第6級
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下:第7級
- 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下:第8級
- 一眼の視力が0.1以下:第10級
- 正面を見た場合に複視の症状を残すもの:第10級
- 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの:第11級
- 両眼のまぶたに著しい運動障害を残す:第11級
- 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの:第11級
- 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残す:第12級
- 一眼のまぶたに著しい運動障害を残す:第12級
- 一眼の視力が0.6以下:第13級
- 正面以外を見た場合に複視の症状を残す:第13級
- 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残す:第13級
- 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残す:第13級
- 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残す:第14級
一眼の視力が0.06以下になったもの
怪我によって「一眼の視力が0.06以下になったもの」に該当する場合には後遺障害等級第9級の認定がされます。
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
怪我によって「両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第9級の認定がされます。
「半盲症」、「視野狭窄」及び「視野変状」とは、V/4視標による8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下になった場合のことをいいます。
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
怪我によって「両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第9級の認定がされます。
「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、まぶたを閉じたときに、角膜を完全に覆えないことをいいます。
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
怪我によって「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第9級の認定がされます。
咀嚼(そしゃく)及び言語の機能に障害を残すもの
怪我によって「咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第9級の認定がされます。
「咀嚼機能に障害を残すもの」とは、ある程度固形食は摂取できるが、これに制限があって、咀嚼が十分でないものをいいます。
「言語の機能に障害を残すもの」とは、次の4種の語音のうち、1種の発音ができない場合をいいます。
- 口唇音(ま行音、ば行音、ぱ行音、わ行音、ふ)
- 歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
- 口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
- 喉頭音(は行音)
咀嚼および言語の機能に関する障害については次の通り認定される場合もあります。
- 咀嚼及び言語の機能を廃した:第1級
- 咀嚼又は言語の機能を廃した:第3級
- 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残す:第4級
- 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残す:第6級
- 咀嚼又は言語の機能に障害を残す:第10級
両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
怪我によって「両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」に該当する場合には後遺障害等級第9級の認定がされます。
「両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度」とは次の場合です。
- 両耳の平均純音聴力損失値が50dB以上のもの
- 両耳の平均純音聴力損失値が40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの
聴力に関する障害にはほかにも次のような認定がされることがあります。
- 両耳の聴力を全く失った:第4級
- 耳に接しなければ大声を解することができない程度になった:第6級
- 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった:第6級
- 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの:第7級
- 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの:第7級
- 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になった:第10級
- 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になった:第10級
- 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になった:第11級
- 一耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった:第11級
- 一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になった:第14級
一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
怪我によって「一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」に該当する場合には後遺障害等級第9級の認定がされます。
「一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」とは、1耳の平均純音聴力損失値が70dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力損失値が40dB以上のものをいいます。
一耳の聴力を全く失ったもの
怪我によって「一耳の聴力を全く失ったもの」に該当する場合には後遺障害等級第9級の認定がされます。
「一耳の聴力を全く失ったもの」とは、1耳の平均純音聴力損失値が80dB以上のものをいいます。
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
怪我によって「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」に該当する場合には後遺障害等級第9級の認定がされます。
高次脳機能障害・外傷性脳損傷・脊髄損傷などで認定されます。
高次脳機能障害の場合には次の4つの能力のうち、1つ以上の能力が相当程度が失われている場合がこれにあたります。
- 意思疎通能力
- 問題解決能力
- 作業負荷に対する持続力・持久力
- 社会行動能力
外傷性脳損傷によって身体性機能障害として軽度の単麻痺の症状があると第9級の認定がされます。
脊髄損傷の場合、下肢の軽度の単麻痺の症状があると第9級の認定がされます。
ほかにも次のようなケースで第9級の認定がされることがあります。
- 外傷性てんかんで数ヵ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作である又は服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されている場合
- 通常の労務に服することはできるが激しい頭痛により、時には労働に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限される
- 失調、めまい及び平衡機能障害について通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限される
- カウザルギーについて、通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限される
- 反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)について、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限される
神経系統の機能又は精神の障害の程度によって次のような等級に認定されることがあります。
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの:第1級
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの:第2級
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの:第3級
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの:第5級
- 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの:第7級
- 局部に頑固な神経症状を残すもの:第12級
- 局部に神経症状を残すもの:第14級
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
怪我によって「胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」に該当する場合には後遺障害等級第9級の認定がされます。
次のような症状があると「胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」として第9級の認定がされます。
- 多数の臓器に障害を残し、それらが複合的に作用するために、通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種が相当程度に制約される
- 動脈血酸素分圧による判定脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下で、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr以上43Torr以下)にある場合
- 心機能の低下による運動耐容能の低下が中等度(おおむね6METsを超える強度の身体活動が制限されるもの)である場合
- ペースメーカーを植え込んだ
- 房室弁又は大動脈弁を置換して継続的に抗凝血薬療法を行う
- 食道の狭さくによる通過障害を残す
- 消化吸収障害及びダンピング症候群が認められる
- 消化吸収障害及び胃切除術後逆流性食道炎が認められる
- 小腸を大量に切除して残存する空腸及び回腸の長さが100cm以下となった
- 小腸皮膚瘻を残すもので、瘻孔から漏出する小腸内容がおおむね100ml/日以上であるが、パウチ等による維持管理が困難にはあたらない場合
- 便秘を残しており用手摘便を要すると認められる場合
- 便失禁を残すもので常時おむつの装着が必要
- 肝硬変(ウイルスの持続感染が認められ、かつ、AST・ALTが持続的に低値であるものに限る)
- 膵臓の障害により外分泌機能の障害と内分泌機能の障害の両方が認められる
- 腹壁瘢痕ヘルニア、腹壁ヘルニア、鼠径ヘルニア又は内ヘルニアを残すもので、常時ヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるもの、又は立ったときにヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるもの
- じん臓を失っておらず、GFRが30ml/分を超え50ml/分以下
- 一側のじん臓を失ってFRが30ml/分を超え50ml/分以下
- 膀胱の機能の障害によって残尿が100ml以上
- 切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁で常時パッド等を装着しなければならないが、パッドの交換までは要しない
胸腹部臓器の機能の障害がある場合として次の等級に認定される場合があります。
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する:第1級
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの:第2級
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの:第3級
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの:第5級
- 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの:第7級
- 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの:第11級
- 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの:第13級
一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの
怪我によって「一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの」に該当する場合には後遺障害等級第9級の認定がされます。
「手指を失ったもの」とは、親指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったことをいい、具体的には次の通りです。
- 手指を中手骨又は基節骨で切断した
- 近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断した
手指の怪我については他に次の等級に認定されることがあります。
- 両手の手指の全部を失った:第3級
- 両手の手指の全部の用を廃した:第4級
- 一手の五の手指又は親指を含み四の手指を失った:第6級
- 一手の親指を含み三の手指を失った又は親指以外の四の手指を失った:第7級
- 一手の五の手指又は親指を含み四の手指の用を廃した:第7級
- 一手の親指を含み二の手指を失った又は親指以外の三の手指を失った:第8級
- 一手の親指を含み三の手指の用を廃した又は親指以外の四の手指の用を廃した:第8級
- 一手の親指又は親指以外の二の手指の用を廃した:10級
- 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの:11級
- 一手の小指を失ったもの:12級
- 一手の親指以外の手指の指骨の一部を失った:14級
- 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなった:14級
一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
怪我によって「一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの」に該当する場合には後遺障害等級第9級の認定がされます。
「手指の用を廃した」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)に著しい運動障害を残すものであり、具体的には次の状態をいいます。
- 手指の末節骨の長さの1/2以上を失った
- 中手指節関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限される
- 親指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されている
- 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失した
一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
怪我によって「一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの」に該当する場合には後遺障害等級第9級の認定がされます。
一足の足指の全部足指の怪我については以下の等級に認定される可能性があります。
- 両足の足指の全部を失った:第5級
- 両足の足指の全部の用を廃した:第7級
- 一足の第一の足指又は他の四の足指を失った:第10級
- 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃した:第11級
- 一足の第二の足指を失った、第二の足指を含み二の足指を失った又は第三の足指以下の三の足指を失った:第12級
- 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃した:第12級
- 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失った:第13級
- 一足の第二の足指の用を廃した、第二の足指を含み二の足指の用を廃した又は第三の足指以下の三の足指の用を廃した:第13級
- 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃した:第14級
一足の足指の全部の用を廃したもの
怪我によって「一足の足指の全部の用を廃したもの」に該当する場合には後遺障害等級第9級の認定がされます。
「足指の用を廃した」とは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残す場合をいい、具体的には次の通りです。
- 第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失った
- 第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断した
- 中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限される
外貌に相当程度の醜状を残すもの
怪我によって「外貌に相当程度の醜状を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第9級の認定がされます。
「外貌に相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部の長さ5cm以上の線状痕で、人目につく程度以上の場合に認定されます。
外貌に関する後遺症については次のような等級に認定されることもあります。
- 外貌に著しい醜状を残すもの:第7級
- 外貌に醜状を残すもの:第12級
- 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの:第14級
- 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの:第14級
生殖器に著しい障害を残すもの
怪我によって「生殖器に著しい障害を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第9級の認定がされます。
「生殖器に著しい障害を残すもの」とは、生殖機能は残存しているものの、通常の性交では生殖を行うことができないものが該当します。
- 陰茎の大部分を欠損したもの
- 勃起障害を残すもの
- 夜間睡眠時に十分な勃起が認められないことがリジスキャン(R)による夜間陰茎勃起検査により証明されること
- 支配神経の損傷等勃起障害の原因となり得る所見が次に掲げる検査のいずれかにより認められること
- 射精障害を残すもの
- 尿道又は射精管が断裂していること
- 両側の下腹神経の断裂により当該神経の機能が失われていること
- 膀胱頚部の機能が失われていること
- 膣口狭さくを残すもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限る)
- 両側の卵管に閉塞若しくは癒着を残す、頸管に閉塞を残す又は子宮を失った
複数の後遺症によって第9級と認定される場合もある:併合
上記の症状がなくても、複数の軽い後遺症が重なって第9級と認定される「併合」という仕組みがあります。
複数の後遺症がある場合、それぞれの後遺症が第9級より軽い場合でも、併合により等級認定されることがあります。
併合で第9級と認定されるパターンとしては次のケースがあります。
・第10級の症状と第10級~13級の症状がある場合→第10級が1つ上がり、第9級
具体的に該当しない場合でも第9級と認定される場合もある:相当
具体的に第9級の等級に規定されている場合ではなくても、症状から第9級に認定する「相当」という仕組みがあります。
後遺障害等級認定は、後遺障害等級表に規定されていなくても、第9級に相当するような症状がある場合には、第9級として取り扱う場合があります。これが「相当」です。
後遺障害等級第9級の後遺障害慰謝料
後遺障害等級第9級の後遺障害慰謝料の額は次の通りです。
| 基準 | 後遺障害慰謝料の額 |
| 自賠責基準 | 249万円(※2020年3月31日までは245万円) |
| 任意保険基準 | 300万円~350万円程度(※保険会社による) |
| 弁護士基準(裁判基準) | 690万円 |
保険会社が提示のために使う任意保険基準は、裁判所で認定される弁護士基準の半分近く低い額で提示されることがあります。そのため、示談交渉の際にはきちんと弁護士基準による金額を算出し、相手に提示することが必要です。
後遺障害等級第9級の労働能力喪失率
後遺症が残ったときには後遺障害逸失利益の請求ができます。
後遺障害逸失利益の計算は次の計算式によって行われます。
| 基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 |
後遺障害等級第9級に認定された場合、労働能力喪失率は、35/100で計算します。
まとめ
本記事では、後遺障害等級第9級の主な症状と認定基準・慰謝料相場などについて解説しました。
後遺障害等級第9級に認定されると継続的に投薬をしなければならないものもあり、適切な後遺障害等級認定を確実に取得し、補償を得るべきです。
適切な認定を得る、慰謝料についても弁護士基準で計算しなおす、過失割合などの他の要素についてもきちんとした交渉をするためには弁護士に助力を依頼するのが適切です。なるべく後遺障害等級認定のサポート段階から弁護士に相談して、適切な示談金を得ましょう。

