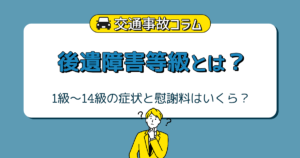手指の後遺症 | 後遺障害認定のポイントは?
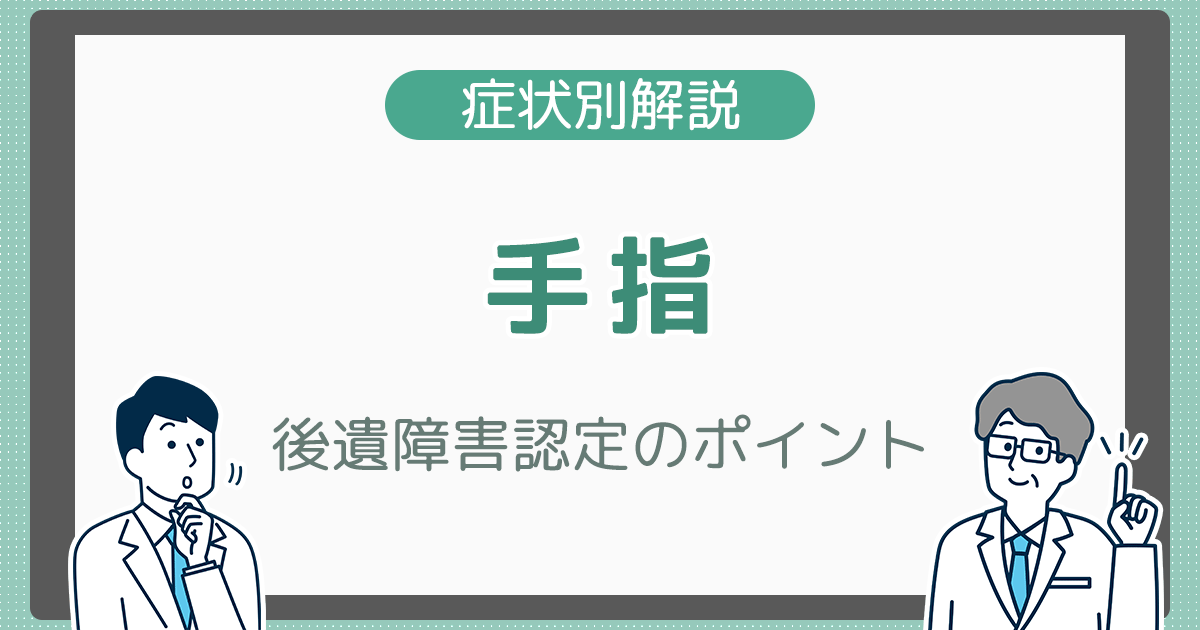
交通事故に遭い、症状固定時に手指に後遺症が残った場合、その症状の内容や程度が、自動車損害賠償法施行令が規定する後遺障害等級表(別表第2)のどの等級に該当するかによって、被害者が得られる損害賠償金が大きく違ってきます。
被害者にとっては、適切な後遺障害等級認定を受けられるかどうかが重要になります。そのためには、交通事故に強い弁護士に依頼すべきだといわれています。
では、手指に後遺症が残った場合、後遺障害認定のポイントは何なのでしょうか。以下においては、手指についての基本的な説明および後遺障害認定のポイントなどについて解説します。
手指の呼称
手指は、一般的に、親指、人差し指、中指、薬指、小指と呼ばれています。本稿では、上述した「後遺障害等級表」の呼称にならい、順次、おや指、ひとさし指、なか指、くすり指、こ指と表記しています。
なお、おや指は、医学用語としては「母指」と表記されます。
手指の構造
手指は、3つの骨(指先の方から、末節骨、中節骨、基節骨。ただし、おや指は末節骨、基節骨の2つの骨)からなっています。 また、手の甲にある5本の骨を中手骨といいます。
そして、おや指には2つの関節、他の指には3つの関節があります。
おや指の場合は、指先に近い方から、末節骨と基節骨の関節を「指節間関節」、基節骨と中手骨の関節を「中手指節関節」といい、おや指以外の指の場合は、指先に近い方から、末節骨と中節骨の関節を「遠位指節間関節」、中節骨と基節骨の関節を「近位指節間関節」、基節骨と中手骨の関節を「中手指節関節」といいます。
手指の後遺障害
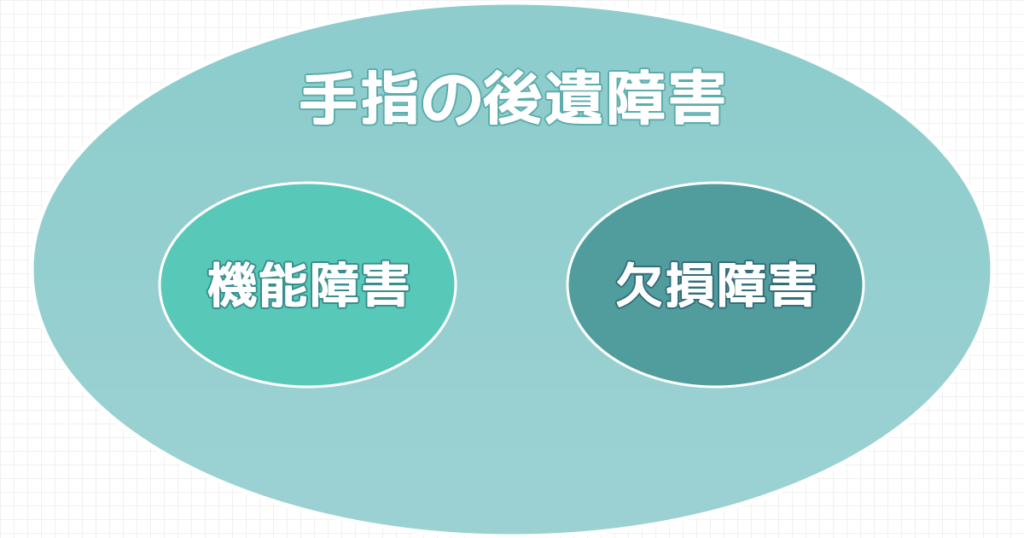
手指の後遺障害としては、欠損障害および機能障害が考えられます。以下で、一つずつ見ていきましょう。
欠損障害
欠損障害とは、手指の全部または一部を失ってしまう障害のことをいいます。
欠損障害の後遺障害等級
- 3級5号(両手の手指の全部を失ったもの)
- 6級8号(1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの)
- 7級6号(1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの)
- 8級3号(1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの)
- 9級12号(1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの)
- 11級8号(1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの)
- 12級9号(1手のこ指を失ったもの)
- 13級7号(1手のおや指の指骨の1部を失ったもの)
- 14級6号(1手のおや指以外の手指の指骨の1部を失ったもの)
用語の説明(クリックで開閉)
- 「手指を失ったもの」とは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいい、具体的には、㊀手指を中手骨または基節骨で切断したもの、㋥近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断したものの場合がこれに該当します。
- 切断とは、手指が骨の部分で切り離された状態をいいます。
- 離断とは、手指の関節の部分で切り離された状態をいいます。
- 「指骨の1部を失ったもの」とは、1指骨の1部を失っている(遊離骨片の状態を含みます)ことがX線写真等により確認できるものをいいます(後記「機能障害」の1に該当するものを除きます)
- 遊離骨片とは、骨が欠片の状態になって離れてしまうことをいいます。
機能障害
機能障害とは、手指の関節の可動域が制限されてしまう障害のことをいいます。
機能障害の後遺障害等級
- 4級6号(両手の手指の全部の用を廃したもの)
- 7級7号(1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの)
- 8級4号(1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの)
- 9級13号(1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの)
- 10級7号(1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの)
- 12級10号(1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの)
- 13級6号(1手のこ指の用を廃したもの)
- 14級7号(1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの)
用語の説明(クリックで開閉)
- 「手指の用を廃したもの」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害(動きにくくなってしまう障害)を残すものをいい、具体的には、㊀手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの、㋥中手指節関節または近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)の可動域が健側(障害のない側)の可動域角度の1/2以下に制限されるもの、㊂おや指については、橈側外転または掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているもの、㊃手指の末節の指腹部および側部の深部感覚および表在感覚が完全に脱失したもの(医学的に当該部位を支配する感覚神経が断裂し得ると判断される外傷を負った事実を確認するとともに、筋電計を用いた感覚神経伝道速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定します)の場合がこれに該当します。
- 橈側外転とは、なか指の基本軸から橈側(橈骨とおや指のある側)へ遠ざかる動きのことをいいます。
- 掌側外転とは、おや指の基本軸から遠ざかる動き(手掌方向への動き)のことをいいます。
- 深部感覚とは、指が振動を感じたり(振動覚)、指がどこにあるかを感じたり(位置覚)、指の動く方向を感じたり(運動覚)する感覚のことをいいます。
- 表在感覚とは、指が物に触れるのを感じたり(触覚)、指が何かに押されるのを感じたり(圧覚)、指が暖かいものや冷たいものを感じたり(温冷覚)、指の表面が傷ついて痛みを感じたり(痛覚)する感覚のことをいいます。
- 感覚の完全脱出とは、表在感覚のみならず深部感覚をも消失したものをいいます。表在感覚のみならず、深部感覚をも完全に脱失するのは、外傷により感覚神経が断裂した場合に限られます。
- 感覚神経伝道速度検査とは、感覚神経を皮膚上より電気刺激し得られた波形から異常部位を判別する検査をいいます。
- 感覚神経活動電位(SNAP)とは、直接神経を刺激して誘発された電位であり、神経線維の活動電位の合計をいいます。
- 「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは、㊀遠位指節間関節が強直したもの、㋥屈伸筋(指の関節を曲げたり、伸ばしたりする際に働く筋肉のこと)の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないものまたはこれに近い状態にあるもののいずれかに該当するものをいいます。
- 関節の強直とは、関節の完全強直(関節が全く動かない状態)またはこれに近い状態にあるものをいいます。
- 「これに近い状態」とは、関節可動域が、原則として健側(障害のない側)の関節可動域角度の10%程度以下に制限されている状態をいいます。
- 10%程度とは、健側の関節可動角度の10%に相当する角度を5度単位で切り上げて計算した角度をいいます。
後遺障害認定のポイント
手指の後遺障害認定のポイントは、どのようなものなのか、以下で見てみましょう。
- 欠損障害
- 機能障害
- 画像検査
- 後遺障害診断書の記載
欠損障害
手指の欠損障害(指骨の1部欠損も含みます)については、外部から見て明らかな場合を除き、画像検査(X線写真、CT画像やMRI画像)で明確に判定される必要があります。
そして、後遺障害診断書には、欠損障害の切断および離断部位の図示が求められます。
機能障害
手指の可動域制限については、原則として他動値(医師が手を添えて曲げた角度)により、さらに必要な場合は自動値(本人が自発的に曲げた角度)を加えて、医師に可動域の測定を正確に行ってもらい、後遺障害診断書にその結果を記載してもらいます。
運動障害を証明するためには、感覚神経が断裂する外傷を受けたことに加え、筋電計を用いた感覚神経伝道速度検査を行う必要があります。
また、可動域制限の原因については、交通事故に遭った直後の診断書や画像検査から客観的に裏付けられる必要があります。
なお、手指の機能障害については、症状の程度を客観的に示さなければ、適切な後遺障害等級認定を受けられないおそれがありますので、X線写真、CT画像やMRI画像の画像検査によってこれを裏付けるようにしましょう。
画像検査
手指の欠損障害および機能障害においては、画像検査が必要なことは上述したとおりです。
なお、手指の損傷については、X線写真では発見できない場合もありますので、手指に異常がある場合には、CT画像やMRI画像で確認するようにしましょう。
後遺障害診断書の記載
後遺障害診断書には、上述した欠損障害、機能障害や画像検査の内容のほか、症状が事故後から症状固定まで一貫して続いていることについても記載してもらいます。
医師は、診断や治療の専門家であって、後遺障害等級認定を行う専門家ではありませんので、医師作成の後遺障害診断書については、弁護士に相談してアドバイスを受けるか、その内容をチェックしてもらうようにしましょう。
まとめ
交通事故により手指に障害を負った場合、その後遺障害としては、上述したように、欠損障害および機能障害の等級認定の可能性があります。
過不足のない後遺障害診断書を作成してもらうためには、弁護士のサポートが欠かせません。
交通事故に遭って手指に後遺症が残り、適切な後遺障害等級認定を受けられるか不安を抱いている方は、是非、交通事故に強い当事務所にご相談ください。